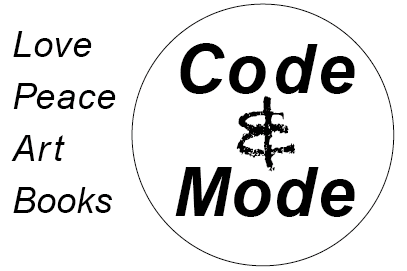1930年代のアメリカでは、経済不況期の連邦美術計画(Federal Art Project, FAP)のようなプロジェクトを実施し、失業中の芸術家に公共的な仕事を依頼して支援した。当時としても、かなり特別なことで、アメリカ唯一のものだった。
ジャクソン・ポロック、アシール・ゴーキー、ウィリアム・デクーニングなどのアーティストたちも多くの芸術家の中に混じって、そこにいた。
時代は、この不況期からさらに第二次世界大戦に入っていく。そして終戦となり、戦後に、この時期のこれらのアーティストたちは、「抽象表現主義」というアメリカ美術を打ち出し、それまでのヨーロッパ中心の美術のあり方に大きなインパクトを与えた。
当時の美術の中心であるフランスには、このような支援はなかった。同時期のドイツでは、国家文化院(Reichskulturkammer)が1933年に設立され、芸術を国家のプロパガンダに利用する一方で、近代美術や前衛芸術を「退廃芸術(Entartete Kunst)」として排除するようになった。一方、ロシアはソビエト連邦下で、社会主義リアリズムが確立され、芸術はその下では支援されるが、表現は規制されていた。そして日本では、日中戦争・太平洋戦争へと向かう中で、芸術・文化活動も次第に国家主義的・軍国主義的になっていっている。
世界的に経済混乱が覆うなかで、各国の対応は、政治的背景をともなって、それぞれ異なるあり方を見せていた。
それでは現在の世界はどうなのだろうか?
アメリカでは、これまで広く採用されていた社会性向上のモットーであるDEI「多様性Diversity、公平性Equity、包括性Inclusion」は、トランプ大統領就任によって排除されることになり、企業経営にこれを採用していた企業は取りやめるようになり、幼稚園から高校までの教育にも"endDEI"が文部省から求められ、さらに大学予算への締め付けを持って、大学をこの路線に従わせようとしている。
社会の混乱は、繰り返してある一定の周期のようにやってくる。社会構造は常に変化しているから、それが周期的なものであるかは不明だが、それでも一定期間をあけて繰り返されるような印象がある。
いまの状況が、果たしてこれからの芸術にどのような影響を与えるのか、現在のアメリカ政府は、1930年代とは、真逆のあり方を示している。
ジャクソン・ポロック、アシール・ゴーキー、ウィリアム・デクーニングなどのアーティストたちも多くの芸術家の中に混じって、そこにいた。
時代は、この不況期からさらに第二次世界大戦に入っていく。そして終戦となり、戦後に、この時期のこれらのアーティストたちは、「抽象表現主義」というアメリカ美術を打ち出し、それまでのヨーロッパ中心の美術のあり方に大きなインパクトを与えた。
当時の美術の中心であるフランスには、このような支援はなかった。同時期のドイツでは、国家文化院(Reichskulturkammer)が1933年に設立され、芸術を国家のプロパガンダに利用する一方で、近代美術や前衛芸術を「退廃芸術(Entartete Kunst)」として排除するようになった。一方、ロシアはソビエト連邦下で、社会主義リアリズムが確立され、芸術はその下では支援されるが、表現は規制されていた。そして日本では、日中戦争・太平洋戦争へと向かう中で、芸術・文化活動も次第に国家主義的・軍国主義的になっていっている。
世界的に経済混乱が覆うなかで、各国の対応は、政治的背景をともなって、それぞれ異なるあり方を見せていた。
それでは現在の世界はどうなのだろうか?
アメリカでは、これまで広く採用されていた社会性向上のモットーであるDEI「多様性Diversity、公平性Equity、包括性Inclusion」は、トランプ大統領就任によって排除されることになり、企業経営にこれを採用していた企業は取りやめるようになり、幼稚園から高校までの教育にも"endDEI"が文部省から求められ、さらに大学予算への締め付けを持って、大学をこの路線に従わせようとしている。
社会の混乱は、繰り返してある一定の周期のようにやってくる。社会構造は常に変化しているから、それが周期的なものであるかは不明だが、それでも一定期間をあけて繰り返されるような印象がある。
いまの状況が、果たしてこれからの芸術にどのような影響を与えるのか、現在のアメリカ政府は、1930年代とは、真逆のあり方を示している。